介護の主要職種一覧とその仕事内容を紹介します

介護職には様々な資格があり、その資格の取り方や受験資格までそれぞれ異なります。
そこで今回の記事では、介護職の主要資格と職種を一挙紹介していきます。
というのも介護の資格だけでなく、もちろん介護職の職種も多様にあり、その職種に応じて必要な資格が異なります。
まずは自分がなりたい職種を見つけて、その職種に必要な資格のとり方をこの記事でチェックしてみてくださいね。
また、それぞれの職種紹介欄には必要な資格も掲載しているので、合わせて参考にしてみてくださいね。
介護の主要職種一覧と仕事内容

冒頭でも触れたように、介護には様々な職種があります。
それに応じて必要な資格が異なりますが、必ずしも全ての職種が資格必須というわけではありませんので、その点は注意しておきましょう。
介護・ヘルパー・訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)などが対象者の自宅を直接訪問し、入浴や排せつ、食事などの「身体介助」や調理、洗濯、掃除などの家事といった「生活援助」、そして通院サポートを行う仕事です。
介護・ヘルパー・訪問介護の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
介護・ヘルパー・訪問介護の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
ホームヘルパーになるには、「介護職員初任者研修」「介護職員実務者研修」「介護福祉士」いずれかの資格を取得しなければなりません。
ただし、訪問介護として働く場合には、無資格でも家事の代行などは行なえるので、介護の経験を積む最初の仕事として選ぶ方も多いです。
ケアマネージャー

介護サービスの計画立案を行い、介護サービスのトータルコーディネーターの役割を担う職業です。
ケアマネージャーの詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
ケアマネージャーの詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
直接、対象者の身体介護や生活介助をするわけではありませんが、対象者やその家族にケアプランを提案・作成し、サービスを提供する自治体や業者と調整する橋渡し的な役割を担います。
ケアマネージャーになるには、生活相談員や支援相談員、相談支援員、主任相談支援、いずれかでの実務を5年間経験し、介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければなりません。
生活相談員(ソーシャルワーカー)

ソーシャルワーカーとも呼ばれる生活相談員は、介護施設などで対象者とその家族との相談対応や、他施設・他職種・他機関との調整役を担います。
生活相談員(ソーシャルワーカー)の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
生活相談員(ソーシャルワーカー)の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
直接ケアプランを作成することはしませんが、介護サービスにおいてマルチに活躍する仕事といえるでしょう。
生活相談員になるための資格は、自治体によって異なります。
社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事専任用資格などが求められやすいです。
機能訓練指導員

介護保険法によって定められているリハビリ分野における職種で、対象者の障害程度や能力に応じたリハビリプランを立案・実施し、自立した生活を送れるようにサポートする職業です。
機能訓練指導員の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
機能訓練指導員の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
機能訓練指導員という資格はありませんが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの資格を持っていなければなりません。
保有している資格によって仕事内容も変わります。
たとえば、理学療法士ならば日常における運動能力の改善、作業療法士であれば心と体のケア、言語聴覚士ならばコミュニケーションや言語訓練の改善が主な仕事内容です。
介護事務

介護サービスを提供する事業所などで事務をする仕事で、介護保険の知識が必要な介護給付費明細書の作成や、介護施設の受付、ケアマネージャーのサポートなどが主な仕事です。
資格や実務経験が必要なくても就ける仕事なので、介護業界で働いてみたい人は検討してみるといいでしょう。
管理・経営者
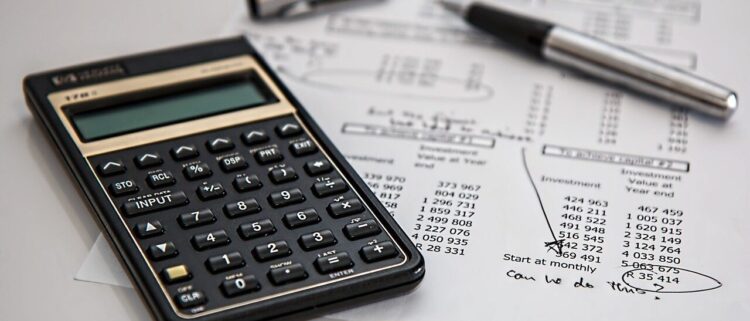
介護施設全体をまとめる「施設長」「管理者」は、施設の運営に関わる一切の管理を行います。
管理・経営者の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
管理・経営者の詳細情報と必要となる資格
(クリックで表示されます)
利用者や従業員の管理だけでなく、施設の運営管理や収支管理など、「ヒト、モノ、カネ」に関わること全てと言っていいでしょう。
施設の運営をメインとした仕事なので、介護の具体的な知識は必要ないかもしれませんが、施設によっては、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護福祉士、介護支援専門員実務研修、社会福祉士のいずれかの資格が必要な場合もあります。
就職を有利に進めるには、資格を持っていた方がいいでしょう。
介護の主要資格一覧と取り方

介護の資格は多種多様で、民間のものから国家資格まで様々。
さらに資格によって個人で受験できるものから、スクールなどに通う必要があるものまであります。
この章では、そんな介護資格の資格概要と資格のとり方について紹介します。
介護職員初任者研修
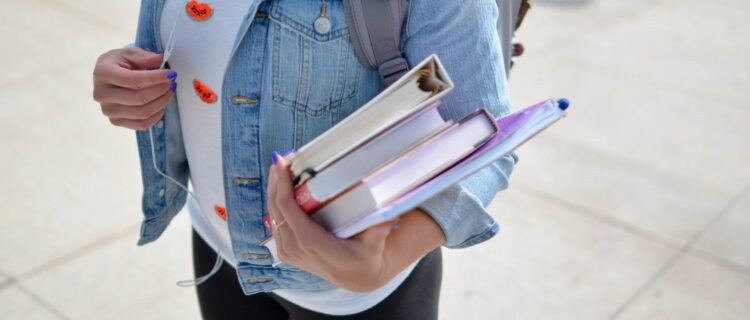
介護職員初任者研修は、「在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術を習得する研修」です。
介護の基礎知識とスキルを証明するための入門資格であり、介護の資格の中でも3カ月程度で取得できるため、比較的簡単に取りやすい資格として知られています。
介護職員初任者研修の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
介護職員初任者研修の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
介護職としてのキャリアをスタートしたい人は、ぜひ取得を検討するといいでしょう。
なお、2013年4月の制度変更までは「ホームヘルパー2級」と呼ばれており、いまでも「ヘルパー2級」と呼ばれるケースもあります。→介護職員初任者研修の資格詳細はこちら
介護職員初任者研修の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
介護職員初任者研修の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
介護職員初任者研修を取得するには、初任者研修講座を開講しているスクールに通い、130時間(10項目)のカリキュラムを修了したら、筆記の修了試験で合格が必要です。
なお、通信による学習も可能ですが、上限が40.5時間と決められているので、通信学習のみでの取得はできません。
以前のヘルパー2級では、介護施設で約5日間の実習が必要でした。しかし、介護職員初任者研修となってから、実習は廃止されています。ただ、介護の現場を体験できる実習は大切な機会なので、スクールによっては任意で実施しているようです。→介護職員初任者研修の資格難易度はこちら
介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修は、基本的な介護提供能力の習得を目標としている研修で、「介護過程の展開」、「医療的ケア」などの実践的な介護技術を身に付けられる資格です。
介護職員初任者研修の上位資格であり、より実践的でレベルが高い研修内容となっています。
介護福祉士実務者研修の詳細を確認する (クリックで表示されます)
介護福祉士実務者研修の詳細を確認する (クリックで表示されます)
かつての「ホームヘルパー1級」と「介護職員基礎研修」を一本化した後継資格として位置づけられています。
また、後述する実務経験ルートで介護福祉士を受験するためには、実務経験3年以上に加えて取得していなければなりません。
介護福祉士実務者研修の資格の取り方を確認する (クリックで表示されます)
受験に条件はなく、無資格からでも受けることが可能ですが、初任者研修を取得していることで免除される科目があります。
実務者研修のカリキュラムは、全20科目、受講時間は合計で450時間。
通信でも学ぶことはできますが、スクーリングが必須な科目もあるため
介護福祉士

介護福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいた国家資格であり、社会福祉の増進に寄与することを目的とした資格です。
責任者や管理者の役職に就くためには介護福祉士の資格を必要とすることが多く、取得には幅広い専門知識が必要となります。
介護福祉士の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
介護福祉士の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
介護福祉士は専門知識とスキルを活かし、利用者のケア、介護スタッフの教育や指導などを行います。
介護関連の資格でも国家資格ということもあり、キャリアアップするためには重要なので、介護職を続けていこうと考えている人はぜひ取得するをおすすめします。→介護福祉士の資格詳細はこちら
介護福祉士の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
介護福祉士の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
介護福祉士の受験するには以下4つのルートがあります。
- 養成施設ルート
- 実務経験ルート
- 福祉系高校ルート
- 経済連携協定(EPA)ルート
ルートによって受験資格を得る方法は異なります。
介護福祉士の資格取得についてはこちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
介護関連の資格の中では難易度は高い方ですが、合格率は70%前後となっています。→介護福祉士の資格難易度はこちら
ケアマネージャー

ケアマネージャーの資格は、介護系資格のなかでも、取得難易度の高い資格です。
ケアマネージャーは、言うならば介護職の管理のため、実務経験も求められます。
ケアマネージャーの詳細を確認する
(クリックで表示されます)
ケアマネージャーの詳細を確認する
(クリックで表示されます)
ケアマネージャーは主に下記のような仕事を行います。
- 要介護認定の調査
- 要介護認定申請代行
- 観察・分析
- ケアプランの作成
- サービス事業者との連絡調整
他の介護職とは異なり、事務的な仕事がメインとなる職種です。→ケアマネージャーの詳細はこちら
ケアマネージャーの資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
ケアマネージャーの資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
ケアマネジャーになるためには、勤務先、または住居地の都道府県で年に1回実施される「介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネージャー試験)」に合格するのが条件。
次に実務研修を受け最後に各都道府県への登録が必要です。
また試験を受けるには指定された業務で「5年以上かつ、日数が900日以上」の業務経験年数が必要となります。→ケアマネージャーの資格についてはこちら
作業療法士

作業療法士はリハビリテーションの分野における専門職の一つで、その名の通り“作業”に焦点を当てた治療・支援を行います。
作業療法士は心身の障害の程度や目標に応じた作業療法を患者さんと考え、その人らしい生活を取り戻す、もしくは作り出すのが目的です。
作業療法士の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
作業療法士の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
そもそも作業療法とは、心身の障害がある方に対して様々な作業を用いる療法のことです。
ここでいう“作業”とは手工芸のような細かな手作業ではなく、日常生活に関わる全ての諸活動および目的や意味を持つ生活行為を指します。
たとえば食事や着替え、家事、余暇活動も“作業“として位置づけられ、病気や怪我をはじめとする何らかの理由でそれらの作業(活動)がうまくできなくなった時こそ作業療法士の出番となるのです。→作業療法士の詳細はこちら
作業療法士の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
作業療法士の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
作業療法士国家試験の受験資格を得るためには、厚生労働大臣または文部科学大臣指定の養成学校(3年以上)を卒業している必要があります。
4年制の大学や専門学校、3年生の短大や専門学校が選択肢となりますが、在学中に専門的な知識を習得したいなら4年制大学、早く就職して現場に出たいなら3年生の学校を選びましょう。
指定養成施設を卒業および卒業見込みであれば、毎年2月に実施されている作業療法士国家試験を受験できます。→作業療法士の資格についてはこちら
レクリエーション介護士

レクリエーション介護士は、介護に関わる専門知識などを取り入れながらレクリエーションを提供する職業です。
レクリエーション介護士の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
レクリエーション介護士の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
基本的には、レクリエーション介護士の業務だけではなくて、介護職員と兼務して業務を行っています。
具体的にレクリエーション介護士の業務目的については、主に以下2つです。
- 介護予防
- 精神的な健康促進
レクリエーション介護士は、高齢者とのコミュニケーション能力の向上や、レクリエーションスキルを身につけることを目的にしている資格です。→レクリエーション介護士の詳細はこちら
レクリエーション介護士の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
レクリエーション介護士の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
レクリエーション介護士には1級と2級に分けられており、2級に関しては受験資格がなく、誰でも受験が可能です。
1級になると2級の取得が必須となり、一人ひとりに合わせたレクリエーションのアレンジ能力など、様々なスキルが必要になります。
福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、車椅子や歩行器といった福祉用具の選び方や使い方の相談に乗り、要介護者やその家族などのサポートを行う福祉用具の専門家です。
介護保険制度の指定を受けている福祉用具のレンタル・販売事業所には、必ず2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務付けられています。
福祉用具専門相談員の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
福祉用具専門相談員の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
福祉用具専門相談員の主な勤務先は介護保険の指定を受けた福祉用具のレンタル・販売事業所です。
また、介護関連の法人以外でも、ホームセンターやスーパーなどの介護用品売り場や、バリアフリー工事を行うリフォーム業者など、福祉用具専門相談員の活躍の場が広がっています。
これは、福祉用具の需要増加につき、介護関連の事業所でなくても介護保険の指定を受けて福祉用具を取り扱っている場所が増えたためです。→福祉用具専門相談員の詳細はこちら
サービス提供責任者の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
サービス提供責任者の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
福祉用具専門相談員は福祉用具の適切な使い方や選び方をアドバイスする専門職なため、介護や福祉用具に関する専門的な知識が求められます。
そのため、福祉用具専門相談員として働くには資格ではなく講習の修了が必要となります。
福祉用具専門相談員指定講習の受講に特別な資格は必要なく、各都道府県が指定した研修機関で誰でも受けることができます。→福祉用具専門相談員の資格についてはこちら
サービス提供責任者

訪問介護のサービス提供責任者は、名前の通り責任者となるので、仕事内容は多岐にわたります。
連絡調整や書類作成のような事務仕事から、実際に現場へ出て訪問介護を行うこともあるので、介護系の仕事のなかでも、仕事量は多い方です。
サービス提供責任者の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
サービス提供責任者の詳細を確認する
(クリックで表示されます)
アセスメント、訪問介護計画書、サービス提供手順書、モニタリングの書類作成を行います。
この書類作成だけでもなかなかの重労働ですが、これに加えて訪問介護サービス提供責任者は、ときに現場に出てヘルパー業務も行わなければいけません。
とくに事業所の人員が不足しているときは、ヘルパーとしての仕事も兼任しなければいけないのです。→サービス提供責任者の詳細はこちら
サービス提供責任者の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
サービス提供責任者の資格の取り方を確認する
(クリックで表示されます)
誤解される事が多いですが、サービス提供責任者という資格はありません。サービス提供責任者というのは、あくまで職種・役割を指すことばであり、サービス提供責任者になるための資格や研修があるわけではないのです。
しかし、サービス提供責任者になるために必要な資格はあります。→サービス提供責任者になるための資格はこちら










