生活相談員になるためにはどのような資格が必要か知っていますか?
この記事では「生活相談員の資格」について解説していきます。
結論、生活相談員になるための資格はありません。しかし、資格要件は決められています。
その他にも「生活相談員とケアマネの違い」の説明や、「主な都道府県の資格要件」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んで生活相談員の資格を手にいれていただければ幸いです。
生活相談員とは?

生活相談員はソーシャルワーカーとも呼ばれ、特別養護老人ホームやデイサービス事業所、ショートステイ事業所などの介護施設で活躍しています。
大きな役割は、相談業務や調整業務で、対象者とその家族との相談対応や、他施設・他職種・他機関との調整役です。
具体的な仕事内容は、以下になります。
- 施設の入退所の手続き
- ケアサービスの利用開始や中止に関する業務
- 対象者および家族に対する相談対応
- ケアマネジャー、地域、他機関との連絡や調整
- 施設内の調整
- 介護スタッフのサポート
- 苦情対応
業務の幅が広く、生活相談員が調整することで関係者が同じ情報を共有して支援でき、ケアマネジャーが立てたケアプランの目的に沿った支援も可能となるため重要な役割を担っているといえるでしょう。
施設や求められる業務も変わってくので、臨機応変な対応を求められます。
生活相談員になる際に注意すること

生活相談員になりたいとき、何か資格を取る必要はあるのでしょうか。
結論から言うと、「生活相談員」という資格はないです。
しかし、資格がないからと言って誰もが生活相談員になれるわけでもありません。
そこでここでは、生活相談員になるとき注意すべき3点を紹介します。
- 生活相談員という資格はない
- 都道府県によって必要条件が違う
- 資格がなくても働ける
これから生活相談員になりたい人は、参考にしてください。
生活相談員という資格はない
生活相談員という資格はありません。試験を受けて合格する必要もないので、資格を必要とする他の仕事とは違います。
しかし、誰もが就ける仕事ではなく、要件を満たさなければなりません。
具体的には、以下の資格のいずれかを保有している必要があります。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
未経験であっても、上記の資格のいずれかを保有していれば生活相談員になれる機会があります。
さらに細かい条件は、都道府県によって違うので、次項で詳しく紹介しましょう。
都道府県によって必要要件が違う
生活相談員になる場合、都道府県によっても必要要件が変わるので、それぞれの自治体に確認するといいでしょう。
もし生活相談員になりたい場合、自治体によって生活相談員になる条件が違うので、住んでいる地域の情報を確認してください。
都道府県によっては資格を持っていなくても生活指導になれるかもしれません。資格がないからといって諦めない方がいいでしょう。
資格がなくても働くことができる

社会福祉士や精神保健福祉士などの資格がなくても、都道府県によっては生活相談員になれます。
たとえば2年以上の介護業務の実務経験があれば、生活相談員として認められるケースもあるため、自治体ごとの要件を確認しましょう。
ただし、資格がなくて経験もない場合は、なかなか生活相談員になるのは難しいです。
そのため、資格取得の勉強や対策をするか、現場で経験を積むことをおすすめします。
生活相談員の資格要件

生活相談員になるための資格として、以下の3つがあります。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
都道府県ごとの違いはありますが、生活相談員になるには、上記の資格を取得している方がいいです。
ここでは、それぞれがどんな資格なのか、どうすれば取得できるのかなどを詳しく紹介します。
社会福祉士

社会福祉士は国家資格で、福祉や医療に関する相談援助の専門家です。
高齢者だけでなく、児童まで相手にすることもあり幅広い世代の人と関わる仕事で主な活躍場所は、高齢者や障害者の施設、児童相談所や母子支援施設、医療機関、行政の窓口などになります。
社会福祉士になるには、「社会福祉士国家試験」に合格して、社会福祉士として登録しなければなりません。
「社会福祉国家試験」は、誰もが受験できるわけでなく、下記いずれかのルートを満たした人のみとなるので、注意しましょう。
福祉系の4年制大学を卒業
4年制の福祉系大学で指定科目を履修して卒業した場合は、受験資格を満たしています。
ただし、履修した科目が基礎科目のみの場合、短期養成施設などで必要カリキュラムを6カ月以上履修しなければなりません。
福祉系短大等を卒業
指定科目を履修した福祉系短大等を卒業した場合、3年制なら1年間、2年制なら2年間の相談援助実務を経験すれば、受験資格を得られます。
基礎科目のみ履修の場合も同様で、3年制なら1年間、2年制なら2年間の相談援助実務を経験しなければなりません。
さらに相談援助実務を経験した後、短期養成施設などで必要なカリキュラムを6カ月以上履修する必要があります。
社会福祉主事養成機関を修了
社会福祉主事の任用資格を取得できる「社会福祉主事養成機関」を修了している場合、2年制短期大学を卒業した人と同じで、2年の相談援助実務の経験が必要です。
その後、短期養成施設等で必要なカリキュラムを6カ月以上履修すれば国家試験の受験資格を得られます。
精神保健福祉士
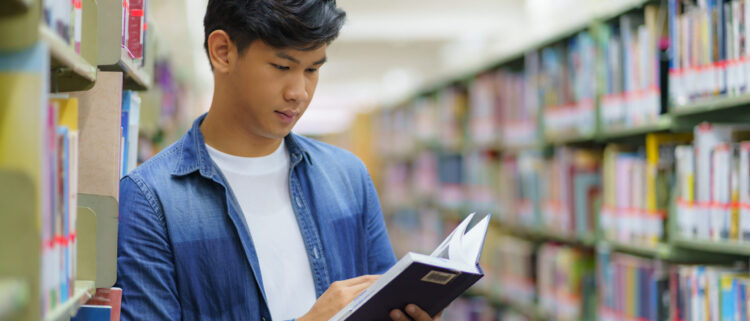
Portrait of Smart Asian man university student reading book and between bookshelves in campus library with copyspace.
精神保健福祉士は、精神保健福祉の領域で専門的な知識と技術を持ち、精神に障がいのある人たちの社会復帰支援や、必要な訓練を行う精神科ソーシャルワーカーです。
幅広い人々を対象にする社会福祉士とは違い、主に精神的な障がいある人への支援が中心になります。
社会福祉士と同じく国家資格であり、「精神保健福祉士国家試験」に合格しなければなりません。
また誰もが受験できるわけではなく、下記いずれかのルートを満たした人のみとなるので注意しましょう。
福祉系の4年制大学を卒業
社会福祉士と同じく、4年制の福祉系大学で指定科目を履修して卒業した場合は、受験資格を満たしています。
ただし、履修した科目が基礎科目のみの場合、短期養成施設などで必要カリキュラムを6カ月以上履修しなければなりません。
福祉系短大等を卒業
指定科目を履修できる福祉系短大等を卒業した場合、3年制なら1年間、2年制なら2年間の相談援助実務を経験すれば、国家試験を受験可能です。
基礎科目のみ履修の場合も同様で、3年制なら1年間、2年制なら2年間の相談援助実務を経験しなければなりません。
さらに相談援助実務を経験した後、短期養成施設などで必要なカリキュラムを6カ月以上履修しなければなりません。
4年制一般大学を卒業
4年制の一般大学の場合は、卒業後に一般養成施設などで指定カリキュラムを1年以上履修すれば、受験資格を得られます。
一般短期大学を卒業
一般短大等を卒業した場合、3年制なら1年間、2年制なら2年間の相談援助実務の経験と、1年以上の一般養成施設などで指定カリキュラムを1年以上履修すれば受験可能です。
社会福祉士の資格を持っている
社会福祉士の資格を持っている場合は、短期養成施設などで指定カリキュラムを6ヶ月履修すれば、受験資格を得られます。
相談援助実務経験がある
相談援助実務経験が4年以上必要で、さらに一般養成施設などで1年以上の指定カリキュラムを履修すれば、受験可能です。
社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格は、都道府県や市町村で社会福祉に関わる仕事を行うための資格です。
なお、「任用資格」とは、公務員として特定の職業に就く際に必要となる資格で、社会福祉主事はその任用資格の一種となります。
社会福祉主事任用資格を取得するための試験はありません。大学や通信教育における科目履修によって取得です。
主な資格取得ルートは、以下になります。
大学または短期大学卒業
大学または短期大学において、たとえば社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論などの「厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目」から3科目以上を修めて卒業すれば取得できます。
所定の学校の通信課程を修了
全国社会福祉協議会が経営する「中央福祉学院の社会福祉主事資格認定通信課程」または「日本社会事業大学の通信教育過程」を修了すれば、資格を取得できます。
指定養成機関を修了
社会福祉主事養成機関で指定の科目(22科目・1,500時間)を修めて卒業すれば、資格を取得できます。
なお、養成機関の多くは2年制または3年制の専門学校です。
都道府県等講習会を受講
都道府県等がおこなう講習会で指定の科目(19科目・279時間)を修めると、資格を取得できます。
社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を保有
すでに社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を持っているならば、社会福祉主事任用の資格も取得できます。
主な都道府県の生活相談員の資格要件

生活相談員の資格要件は、都道府県で違うと説明しました。
基本的には、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のいずれかを持っていれば、生活相談員になることは可能です。
しかし、それ以外にどんな要件があるか、ここでは実際の都道府県を例に紹介します。
- 東京都の場合
- 神奈川県の場合
- 大阪府の場合
東京都の生活相談員の資格要件
東京都の場合、以下いずれかの要件を満たしていれば、生活相談員になれます。
- 介護福祉士の資格を有し、介護施設や事業所で1年以上の実務経験を積んでいる
- 介護支援専門員の資格を有している
- 特別養護老人ホームで、介護の提供に係る計画の作成に関する実務経験が1年以上ある
- 老人福祉施設の施設長をしていた経験がある
参考:社会保険労務士事務所OfficeNearco(オフィスネアルコ)「東京都の生活相談員」
神奈川県の生活相談員の資格要件
神奈川県川崎市の場合、以下いずれかの要件を満たしていれば、生活相談員になれます。
- 介護福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 介護保険施設または通所系サービス事業所で、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護業務に従事した人
参考:川崎市ホームページ
大阪府の生活相談員の資格要件
神奈川県川崎市の場合、介護福祉士もしくは介護支援専門員の資格を有していれば生活相談員になれます。
参考:大阪府ホームページ
介護支援専門員(ケアマネジャー)と生活相談員の違い

生活相談員(ソーシャルワーカー)と介護支援専門員(ケアマネージャー)は、どちらも介護や福祉の現場で活躍する職業なので、似たような仕事内容と思う人もいるかもしれません。
しかし、ケアマネージャーとソーシャルワーカーの業務内容は、明確に分かれています。
介護支援専門員の主な業務は、要介護認定を受けた人やその家族に対して、適切な介護保険サービスを紹介し、実際にサービスを受けるための橋渡しです。
一方で生活相談員の主な業務は、病気や怪我、高齢や障がいなど日常生活に不安のある人やその家族に社会復帰のアドバイスや指導になります。
そのため、生活相談員の方が介護支援専門員よりも幅広い相談を受けることになり、業務の幅も広いと考えておくといいでしょう。
生活相談員に必要なスキルとは?

それでは最後に生活相談員に必要なスキルについて紹介します。
とくに必要なスキルは、以下3つです。
- マネジメントスキル
- コミュニケーションスキル
- ソリューション提案スキル
それぞれ詳しく見てみましょう。
マネジメントスキル
生活相談員は、対象者やその家族の相談を聞いて、さまざまな関係機関との調整やスタッフとの連携をしなければなりません。
関係する人が多いので、うまくマネジメントをしないと予定通りに進まず、対象者とその家族だけでなく、関係者にも迷惑を掛けてしまいます。
事前の根回しや進捗確認などを行い、管理するマネジメントスキルを身につけるといいでしょう。
コミュニケーションスキル
生活相談員は、対象者やその家族、各施設関係者とコミュニケーションを取らなければなりません。
相手によって立場も違うので、気遣いしつつ会話をしていかなくてはならず、「さまざまな人と話すのが得意」だと、生活相談員としてうまくやっていけるでしょう。
ソリューション提案スキル
生活相談員は、対象者やその家族の問題を解決するために行動しなければなりません。
そのためにどんなソリューションがあるのか、提案できるスキルも必要です。
ただ言われたことをやるのではなく、相手の要望をヒアリングし、それに見合う解決方法を提示できれば信頼されるでしょう。
生活相談員の資格を取得して生活相談員になろう

生活相談員の資格について解説しました。
具体的に「生活相談員」という資格はありませんが、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持っていると生活相談員になりやすいです。
ただし、自治体によっては実務経験だけでも生活相談員になれる場合もあるため、住んでいる地域で詳細を確認するといいでしょう。
生活相談員は、対象者やその家族だけでなく、医療施設などさまざまな人とコミュニケーションを取りつつ、調整しなければなりません。
コミュニケーションスキルだけでなく、マネジメントや提案力なども求められます。
これから生活相談員になりたい人は、ぜひ参考にしてください。

