介護事務の資格があることによって、同じ介護の仕事でも差があることをあなたは知っていますか?
この記事では「介護事務の資格と取得難易度」についてわかりやすく解説していきます。
結論、介護事務の資格は取得が簡単なので、ご自身が取りやすい資格を選ぶことが重要です。
介護事務の資格を取得する際、どの資格なら取りやすいかの難易度も調べましたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「介護事務」の仕事内容や特徴、「在宅でも取れる介護事務の資格」について説明していきますので、この記事を読んで介護事務の資格に合格してただければ幸いです。
また「介護事務の仕事内容」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
介護事務は資格がなくても働ける

介護事務と言われていますが、そもそも介護事務として働くために資格は必要ありません。
もちろん介護保険に関する知識は求められますが、基本的に専用のソフトを使うためほとんど自動で保険請求ができてしまいます。
せいぜいが、実際にその介護をやったかどうかの確認程度でしょう。
- 介護保険請求
- 受付事務と電話対応
これらの業務が中心のため、資格よりもWordやExcelの操作といった一般的なPCスキルを求められることの方が多い仕事です。
介護事務の仕事内容とは

介護事務の仕事はさまざまなものがあります。
事業所によってサービスは違いますが、基本的な仕事内容はほとんど同じなのです。
以下のものが代表的でしょう。
- 受付・窓口業務
- 電話対応
- 従業員のシフト管理
- 施設の設備管理
- 介護保険請求の作成
- レセプト作成
雑用的な仕事まで入っているのがわかると思います。
それぞれ見ていきましょう。
受付・窓口業務
介護事務の仕事で受付・窓口で来客対応をすることがあります。
特に小規模な施設の場合、専門の職員がいないため対応するケースが多いです。
来客した相手によっては応接室への対応も必要となるでしょう。
座席案内や飲み物の出し方といった一般的なマナーが求められます。
電話対応
電話対応も介護事務の仕事です。
電話交換手がいない限り、基本的に電話を取るのは事務所で仕事をしている介護事務となるからです。
電話の相手は一般の方や利用者の家族、病院など特に決まった相手はいません。
施設利用者の方が外部の病院に受診する際の調整も行うため、電話対応のスキルが求められます。
従業員のシフト管理

従業員の勤怠管理も介護事務の仕事のひとつです。
大きな施設になると別に人員が配置されている可能性もありますが、小さな施設だと人がいないため介護事務が担当することがあります。
他にも新しく雇用された人に労働条件通知書を作成するといった労務関係の仕事を任されるケースもあります。
施設の設備管理
施設の設備管理も介護事務の仕事です。
定期的に見回りをしたり職員から上がってきたりした設備面の問題を解決するために動くのも、事務の仕事だからです。
設備にトラブルがあった場合は、業者に依頼し立ち会うといったことまで必要となるでしょう。
縁の下の力持ち的な役割を担っています。
介護保険請求の作成
介護保険請求を作成するのも介護事務士の仕事です。
施設を利用した方のご家族へ、受けた介護保険サービスの1~3割を請求します。
その場合の請求書作成を行うこととなります。
支払期限が設定されているため、期限に間に合うように作成しなければいけません。
レセプトの作成

レセプトの作成も介護事務士の仕事です。
むしろレセプトこそが最も大きな仕事と言っても過言ではありません。
レセプトを行うことで得られる介護報酬が、事業所にとって大きな収入源となるためです。
期限内に作成することを求められますが、正確に金額を計算する能力が必要となっています。
レセプトとは?
レセプトとは、利用者が支払う1~3割以外の金額を市町村へ請求する仕組みのことです。
介護保険は社会保障の一環のため、利用者が負担していない7~9割の請求は市町村が負担しています。
介護サービス事業者は、市町村に対して介護給付費明細書を作成することで前月分の介護報酬を得られます。
つまり利用者が支払ってくれた金額よりも大きな収入を得られる可能性がある、大切な仕事なのです。
介護事務では資格よりも即戦力が求められる傾向

介護業界は全体的な人不足なため、介護事務も求められるのは即戦力です。
事務仕事も仕事内容に入ってくるため、資格を必要としない業務が多いのも理由のひとつとなっています。
そのため介護事務として入社してから資格を取得する方も多くいるのが実情です。
資格がなくてもそれまでの仕事の経験から即戦力として採用される可能性も高いでしょう。
介護事務で資格以外で活かせるスキル5選

介護事務では資格以外でも活かせるスキルが多くあります。
その代表的なものが、以下の5つです。
- Word・ExcelなどPCの基礎的な知識
- 電話・窓口対応のスキル
- デスクワークが苦にならない集中力
- 常に新しい知識を勉強し続けられる意識
- 調整力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Word・ExcelなどPCの基礎的な知識
介護事務ではWord・ExcelといったPCの基礎的な知識を活かせます。
なぜなら、介護事務での仕事のほとんどがPCを使っての仕事になるからです。
施設のさまざまな内容のデータ管理やWordを使った文書案内など、枚挙にいとまがありません。
PCの基礎知識は介護事務において、必須とも言える知識です。
電話・窓口対応のスキル
介護事務では電話・窓口対応のスキルがあれば活かせます。
なぜなら、介護事務の業務において電話対応や窓口で対応するのが仕事の1つだからです。
そのため電話・窓口の経験があればスキルとして活かせるのは間違いありません。
デスクワークが苦にならない集中力

介護事務ではデスクワークが苦にならない集中力も活かせます。
というのも、介護事務はそのほとんどがデスクワークになるからです。
PCを使った業務はもちろん、電話・受付対応にいたるまで座った状態で行うことがほとんどとなっています。
デスクワークが苦にならないほどの集中力を発揮できる人は、そのスキルを上手く活かせます。
常に新しい知識を勉強し続けられる意識
介護事務では、常に新しい知識を勉強し続けられる意識を持っていると仕事に活かしやすいでしょう。
なぜなら、介護事務のメイン業務である介護保険請求はその内容が3年ごとに改定されるためです。
そのため常に新しい知識を勉強し仕事に反映させられるかが重要となってきます。
業務遂行のために新しい知識に物怖じせずに飛び込める意識が何よりも大切です。
調整力
介護事務では調整力があると仕事に活かせます。
なぜなら、介護事務は事業所と利用者様やそのご家族様との仲介役でもあるからです。
お互いがどのような認識をしているのかをすり合わせられる能力は、双方にとって重要なスキルとなります。
介護事務に国家資格はない

介護事務の資格はいくつかありますが、国家資格はありません。
なぜなら全て民間の団体が主催している民間資格だからです。
介護に関係する国家資格は介護福祉士のみとなっています。
-

-
【必見】60代でも介護職への転職は可能? | 60代だからこその強みと成功のポイントを徹底解説
60代でも介護職へ転職できることをあなたは知っていますか? この記事では「60代から介護職へ転職する方法」について解説していきます。結論、介護職は人手不足な業界なので60代の未経験でも転職が可能です。 ...
続きを見る
介護事務は資格を取っておくと業務上で有利になる

実際に働くとなった場合、資格を取っておく方が有利になるのは間違いありません。
資格を取ることで以下のメリットが得られます。
- 介護保険に関する知識が得られる
- 就職・転職活動で有利になる
- 現場から事務仕事への理解が深まる
- 給料・年収に手当がつく可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
介護保険に関する知識が得られる
資格を取る中で介護保険に関する知識は確実に得られます。
取得していなかったとしても仕事をする上で業務に触れているうちになんとなく理解できますが、理解度は大きく異なります。
特に介護報酬請求を行う際に必要な算定要件は専門的な知識となるため、業務遂行で必要となるでしょう。
就職・転職活動で有利になる
介護業界で働きたいと考えている場合、介護事務の資格を持っていることで有利になります。
特に介護事務は資格がなくてもなれることから、求人の応募者が多い傾向にあります。
そんな中で資格を持っていれば有利に働くことは間違いありません。
介護事務を目指すのであれば、取得して損はないでしょう。
現場から事務仕事への理解が深まる

実際に介護をしている人間が資格を持つことで、介護事務への理解度が深まります。
大きな施設になると現場と事務の間でお互いの仕事内容がわからず、衝突することがままあります。
そういった中で介護事務の資格を取得することで、より深い領域での連携が可能です。
またハードな現場から介護事務へと転身する際にも役立ってくれるでしょう。
給料・年収に手当がつく
介護事務の資格を持っていることで手当がつく可能性があります。
全体的に見ても介護事務の年収は日本の平均年収と比較しても低い傾向です。
| 正社員 | 平均年収370万円 |
| 派遣社員 | 平均時給1,244円 |
| アルバイト・パート | 平均時給990円 |
職場の規模や地域差が大きく出ますが、介護事務の資格を持っていることで手当が加算される可能性があります。
介護事務資格の特徴3選

介護事務の資格は他の資格と比べても珍しい特徴があります。
- 受験資格を設けていない
- 難易度が全体的に低め
- 働きながらでも独学で取得しやすい
これらのことがあるため、取得しやすい資格です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
受験資格を設けていない
介護事務の資格は全て受験資格を設けていません。
なぜなら介護事務の資格は民間資格であるためです。
そのため国家資格などと違い受験資格が必要なく、誰でも受けられる資格となっています。
難易度が全体的に低め
介護事務の資格は複数ありますが、全体期に難易度が低めです。
各資格の試験合格率が50~70%となっていることからも、一部の国家資格のようなデタラメな難しさがないことは明白でしょう。
学習方法にさえ気をつければ、全く知らなくても4ヶ月程度の独学でじゅうぶんに合格が可能です。
働きながらでも目指しやすい

介護事務は働きながらでも目指しやすい資格です。
ユーキャンなどの有名な通信講座で教材が提供されているため、隙間時間を利用して学習できます。
資格試験が定期的に実施されているのもあって、自分のタイミングで試験を受けられます。
これらのことから、介護事務の資格は働きながらでも目指しやすい資格といっていいでしょう。
介護事務の資格の取り方

介護事務の資格の取り方は、大きくわけて3つあります。
- 介護系の学校に通う
- 通信講座に申し込む
- 独学で勉強する
それぞれ詳しく見てみましょう。
介護系の学校に通う
介護系の学校に通い、専門的な勉強を受ける中で資格を取るのも1つの方法です。
この場合、大学・短大であればカリキュラムの中に組み込まれていることが多いため、自然と取れるでしょう。
社会人の方で仕事をしながら取りたい場合、認定校を見つけて入学するのが一番の近道です。
通信講座に申し込む
通信講座に申し込む方法が、介護事務の資格を取るにあたってもっとも選ばれる方法です。
講座を運営している団体によっては、資格を取った後に就業サポートをしてくれているところもあります。
そういった講座を選ぶことで就職・転職まで有利に進められます。
自分のライフスタイルにあった講座を選ぶようにしましょう。
独学で勉強する
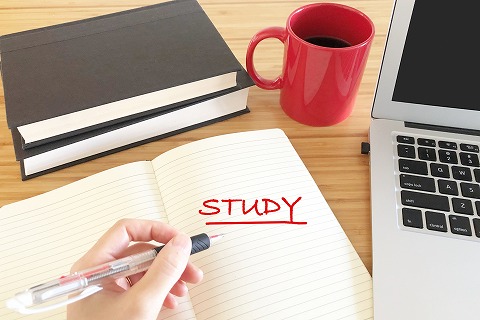
独学で勉強するのも介護事務の資格を取る場合、有効です。
複数の出版社から教材が出ているので、実際に書店に行って使いやすいものを選ぶと良いでしょう。
購入の際に注意したいのが、「最新情報に対応できているか」です。
介護報酬は3年ごとに改定されているため、なるべく中古ではなく最新版を購入してください。
介護事務の資格を独学で取るための勉強方法
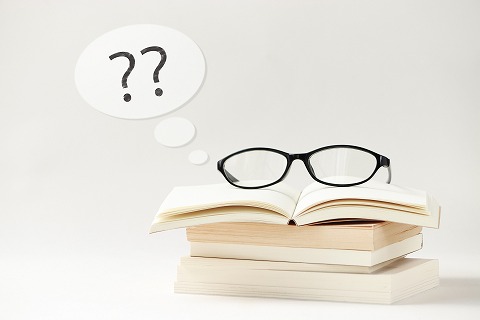
通信講座が多い介護事務の資格ですが、独学での取得ももちろん可能です。
基本的な勉強方法は、他の資格と変わりません。
- テキストを読み込む
- 問題集を何度もやる
これらを仕事終わりに1時間程度勉強するペースで半年ほど続ければ、合格圏内の実力になっていることでしょう。
試験は資料の持ち込みも可能なため、基礎的な知識をしっかりおさえて勉強してくださいね。
介護事務の資格7選
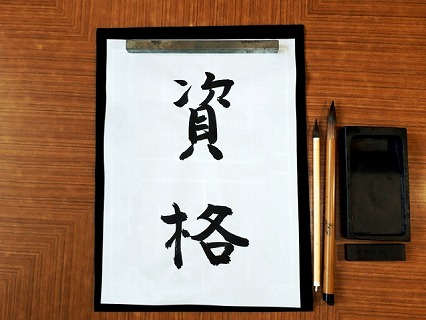
介護事務には全部で7つの資格があります。
| 資格名 | 運営団体 | 試験実施日 | 通信講座の有無 | スクール | 難易度 | 合格率 |
| 介護保険事務士 | つしま医療福祉研究財団 | 講座修了後の指定日 | × | 認定教育機関
介護関連の大学、短期大学、専門学校 |
★★★★★ | 非公開 |
| 介護保険事務管理士 | 日本病院管理教育協会 | 10月・12月 | × | 認定教育機関
介護関連の大学、短期大学、専門学校 |
★★★★☆ | 50% |
| 介護事務管理士(R) | 技能認定振興協会(JSMA) | 奇数月の第4土曜日 | ○ | ソラスト、ユーキャン | ★★★★☆ | 70% |
| 介護事務実務士(R) | 医療福祉情報実務能力協定 | 教育指定校の団体受験のみ | ○ | ヒューマンアカデミー | ★★★☆☆ | 50~60% |
| 介護報酬請求事務技能検定試験 | 日本医療事務協会 | 偶数月第3日曜日 | ○ | 日本医療事務協会 | ★☆☆☆☆ | 84% |
| 介護事務資格 | 日本能力開発推進協会 | カリキュラム修了後随時 | ○ | キャリアカレッジジャパン | 不明 | 非公開 |
| ケアクラーク | 日本医療教育財団 | 5月・9月・1月 | ○ | ニチイ、各専門学校 | ★★★☆☆ | 70% |
合格率が非公開のものもありますが、認定教育機関を出ていないと受けられない資格が一部あります。
それぞれ詳しく見てみましょう。
介護保険事務士
介護保険事務士は「一般財団法人つしま医療福祉研究財団」が主催、認定している介護事務の資格です。
認定教育機関もしくは大学・短大・専門学校でカリキュラムを履修し、試験に合格すれば取得できます。
そのため学校への入学が必須です。
試験日は各認定教育機関により違うため、教育機関を経由して介護事務の資格を取得する場合は事前に確認しておきましょう。
介護保険事務管理士
介護保険事務管理士は「一般財団法人日本病院管理教育協会」認定している介護事務の資格です。
介護保険事務士と同じく、認定教育機関もしくは大学・短大・専門学校でカリキュラムを履修し、試験に合格することで取得できます。
在学中であることが前提となっているため、在学中か今後介護関連の学校に通学しようと考えている方向けです。
介護事務管理士(R)
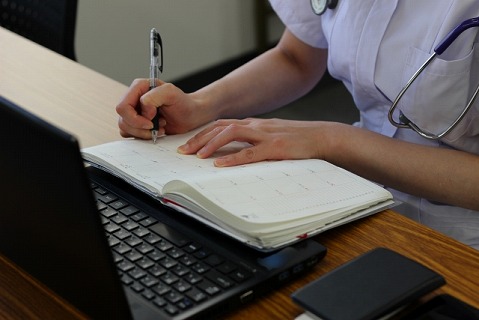
介護事務管理士(R)は、介護事務以外にもケアマネージャーの業務サポートが可能な資格です。
そのため合格基準が難しめとなっています。
しかし取得すれば介護施設はもちろん、国保連合会・保険請求審査期間・損害保険会社などさまざまな分野で活かせます。
さまざまなキャリアで活かせる難易度に見合った資格です。
| 主催 | JSMA 技能認定振興協会 |
| 受験条件 | 誰でも |
| 試験日 | 奇数月の第4土曜日 |
| 在宅試験 | 可 |
| 試験内容 | 学科(マークシート形式10問):①法規、②介護請求事務 |
| 実務(3問):①レセプト点検問題、②レセプト作成 | |
| 合格率 | 50% |
| 合格条件 | 学科試験:100点満点中70点以上 実技試験:70%以上(ただし、1問の得点が50%未満の場合は不合格) |
| 受講料 | 5,500円(税込) |
介護事務実務士(R)
介護事務実務士(R)は、現在介護の仕事をしている方や、今後介護業界でスキルアップを目指す方向けの資格です。
近年増えている長期療養型病床を持っている大規模な医療機関で必要とされている保険請求の能力を見つけられます。
介護保険請求業務以外にも受付・窓口業務を担当することも多い業務で重宝されます。
したがって資格取得後の需要は期待できるでしょう。
| 主催 | 医療福祉情報実務能力協会 |
| 受験条件 | 誰でも |
| 試験日 | 認定教育指定校による |
| 在宅試験 | 不可 |
| 試験内容 | 学科(20問):①介護保険法および関連法規、②介護保険制度、③介護報酬の請求 |
| 明細書作成(3問):介護給付明細書の作成 | |
| 合格率 | 50~60% |
| 合格条件 | 非公開 |
| 受講料 | 7,700円(税込) |
介護報酬請求事務技能検定試験
介護事業所や介護施設など介護事務を必要とされる場所で働くために必要な知識と技能を見つけられる認定試験です。
この資格を取得することによって介護業界に就職・転職時に有利に働くのは間違いありません。
受験申請されすれば一般の方でも申し込める資格です。
| 主催 | 日本医療事務協会 |
| 受験条件 | ・日本医療事務協会が認定する介護事務講座を修了した者 ・受験申請のあった高校・専門学校・短期大学・大学など ・受験申請のあった一般受験申し込み者 |
| 試験日 | 偶数月の第3日曜日 |
| 在宅試験 | 不可 |
| 試験内容 | 学科:学科試験 |
| 実技:診療報酬明細書の作成 | |
| 合格率 | 80% |
| 合格条件 | 非公開 |
| 受講料 | 6,600円(税込) |
介護事務資格

介護事務資格は、「介護管理専門秘書認定資格」とも喚ばれている資格です。
介護報酬請求・介護福祉制度・ケアマネージャーへのサポート業務といったさまざまな技能を見つけていると証明できます。
特に介護が中心となるグループホームや有料老人ホームなど介護業界で働きたい場合に重宝するでしょう。
| 主催 | 一般財団法人日本応力開発推進協会 |
| 受験条件 | 指定の認定教育機関のカリキュラムを終了している |
| 試験日 | カリキュラム修了後、随時 |
| 在宅試験 | 可 |
| 試験内容 | 学科試験のみ |
| 合格率 | 非公開 |
| 合格条件 | 得点率70%以上 |
| 受講料 | 5,600円(税込) |
ケアクラーク
ケアクラークは、介護保険制度や介護事務業務にくわえ、高齢者や障害者まで担当できる資格です。
そのため介護以外にもコミュニケーションの技法や社会福祉援助技術なども学びます。
資格を取る際に学ぶ範囲が広いことから、一度取得すれば介護以外の福祉業界でも活躍が期待できます。
| 主催 | 一般財団法人日本医療協会財団 |
| 受験条件 | 誰でも |
| 試験日 | 5月・9月・1月 |
| 在宅受験 | 不可 |
| 試験内容 | 学科(25問):介護事務知識・筆記(択一式)(50分) |
| 実技(2問):介護報酬請求事務・介護給付費明細書作成(60分) | |
| 合格率 | 非公開 |
| 合格条件 | 学科および実技試験の得点率が70%以上 |
| 受講料 | 6,900円(税込) |
介護事務の資格試験は資料の持ち込みが可能

介護事務の資格の試験は、資料の持ち込みが許可されています。
そのため試験に向けて無理に暗記する必要はありません。
一方で試験内容は専門的な知識が必要なため、確実に合格を目指すなら効率的な学習が必須です。
在宅受験が可能な資格試験も同様に、制限時間内に素早く問題を解けるように勉強するようにしましょう。
在宅でも取れる介護事務の資格

介護事務の資格は在宅で勉強するだけで取れるものがいくつかあります。
仕事などで学校に行けない方には非常に便利ですので、ぜひ活用してください。
在宅で取得可能となっている資格は、以下になります。
| 資格 | 運営会社 |
| ケアクラーク | ニチイ |
| 介護事務資格 | 日本介護事務協会 |
| 介護事務管理士(R) | ユーキャン |
| 介護事務実務士(R) | ヒューマンアカデミー |
| 介護報酬成句湯事務技能検定 | 日本医療事務協会 |
どの試験も試験内容や合格基準が似ているため、取りやすい資格を勉強するのがオススメです。
介護事務と介護事務管理士って何が違うの?

介護事務と介護事務管理士とありますが、同じです。
先述したように民間資格のため名称が統一されていないため、同じ資格でも名称が違っています。
介護事務と介護事務管理士の両方がいる組織の場合、介護事務管理士の方がレセプト業務が多い傾向にあります。
これは、資格を取る際にレセプト関連の勉強をするからです。
介護事務管理士とケアクラークって何が違うの?

介護事務管理士とケアクラークはほとんど同様の仕事内容ですが、細部で違ってきます。
- 介護事務管理士の仕事内容
- ケアクラークの仕事内容
それぞれ詳しく見てみましょう。
介護事務管理士の仕事内容
介護事務管理士の仕事内容は、主に介護請求と介護報酬算定が中心です。
事業所にとって大切な収益面での仕事が多くなります。
そのため一般的なパソコン操作など、請求書作成でのスキルを求められます。
また電話や来客対応も担当することが多いです。
ケアクラークの仕事内容
ケアクラークの仕事内容は、請求面の他に介護に関連する事務全般です。
そのため介護事務管理士よりも肉体労働が増える可能性があります。
利用者様の送迎も覚悟しておいた方が良いでしょう。
介護事務管理士とケアクラークに向いている人

介護事務管理士とケアクラークはほとんど仕事内容が同じですが、担当する仕事量に幅があります。
そのため実際に自分がどちらに向いているのか悩む方も多いでしょう。
以下を参考にしてください。
- 介護事務管理士:30~40代で転職を考えている人
- ケアクラーク:これから就職を目指す人や、介護で実務経験がある人
それぞれ見ていきましょう。
介護事務管理士に向いている人
介護事務管理士に向いているのは、30~40代で介護業界へ転職を考えている人でしょう。
なぜなら電話や来客対応をすることが多く、相手に不快な思いをさせないための能力が求められるからです。
即戦力を求められる仕事でもあるため、それなりに経験を積んでいる年齢の方が向いています。
ケアクラークに向いている人
ケアクラークに向いているのは、これから介護などの福祉業界へ就職をしたいと考えている人でしょう。
クラークの業務は介護業界だとどこにいっても通じる仕事内容のため、転職の際にも有利に働きます。
同様に既に介護で実務経験がある人も、一定の知識を既に持っているためケアクラークとして働きやすいです。
介護事務の資格を持つことで有利になれる求人先

介護事務の資格は、介護業界では引く手あまたな資格です。
資格がなくても問題ないためか、事業所によっては資格のない人が担当していることも多くあります。
そんな中で介護事務の資格を持っていれば、それだけで有利になれます。
特に以下の施設は要チェックです。
- デイサービス
- 介護付有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院のある病院
- 訪問看護ステーション
- 在宅介護支援センター
- 福祉用具レンタル事業所
- 介護人材派遣
これらの事業所で求人の募集があればチャンスなので応募をオススメします。
介護事務の資格を持っている人を求めている事業所は多い

介護事務の資格を持っている人は、事業所において欲しい人材の1つです。
しかし求人サイトで募集するとそれだけでお金がかかるため、人手不足ながら募集をあけていない事業所も多々あります。
特に介護業界は慢性的な人不足です。
事業所に直接電話してみるなど、自分で突撃してみるのも良い方法でしょう。
介護事務の資格を使って就職するときの志望動機の書き方

引く手あまたとはいえ、介護事務の資格を持っていても志望動機はしっかり書かなければいけません。
基本的には一般の就職と同じですが、ポイントとして以下を意識しておきましょう。
- なぜ事務職ではなく介護事務を選んだのか
- なぜこの施設を選んだのか
これらを理由付けすることが何よりも大切です。
なぜ事務職ではなく介護事務を選んだのか
介護事務で就職するなら間違いなく聞かれる定番の質問です。
同じような仕事では普通の事務や医療事務もあります。
なぜ介護の業界を選んだのかを理由付けしましょう。
マニュアル通りの答えは面接する側も聞き飽きているので、自身の介護エピソードとからめるなどリアルな経験があると良いですよ。
なぜこの施設を選んだのか
ほとんどの人は「家が近いから」「給料がいいから」でしょうが、正直に答えてはいけません。
なぜこの施設を選んだのかを明確に答えられるうようにしましょう。
マイナス面をプラスに変える方法もオススメです。
家が近いなら、長く働けることや交通費がかからないこと、地域に詳しいなどがメリットとして使えます。
参考にしてくださいね。
介護事務の資格を取れる講座でサポートがあるもの

介護事務の資格は、そのほとんどが通信講座で取れます。
過度な期待は禁物ですが、講座の中には就業サポートをしてくれているものがあります。
講座の中には自分たちが人材紹介をしている会社もあるため、利用することで就業の幅が広がりますよ。
| 主催者名 | 取れる資格 | 講座の種類 | 就業サポート |
| ヒューマンアカデミー | 介護事務士 | 通信 | ・就職・転職サポート体制あり ・関連会社が求人サイトを運営 |
| 日本医療事務協会 | 介護報酬請求事務技能検定試験 | 通学 / 通信 | ・就職支援事業部あり ・提携機関への派遣、紹介 |
| 三幸福祉カレッジ | 介護事務 | 通学 / 通信 | ・就職支援事業部あり ・定型機関への派遣、証お買い |
| ソラスト | 介護事務管理士(R) | 通信 | ・就職先の斡旋はなし ・自社で介護施設を運営 |
| ニチイ | ケアクラーク | 通学 / 通信 | ・就職先の斡旋はなし ・自社で介護施設を運営 |
介護事務の資格は取得しやすく役立ちやすい

介護事務の仕事は、資格を持っていなくてもできる仕事内容がほとんどです。
しかし介護報酬請求といった専門的な分野になると、資格のあるなしが大きく関わってきます。
介護事務の資格は全て民間資格であるために受験資格が設けられていません。
難易度も高くなく、通信講座を使って独学での勉強でも合格を狙える資格といっていいでしょう。
忙しい時間の合間に勉強をしてもじゅうぶんに取得可能な資格なので、ぜひ挑戦してくださいね。


